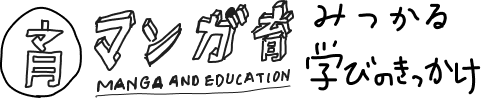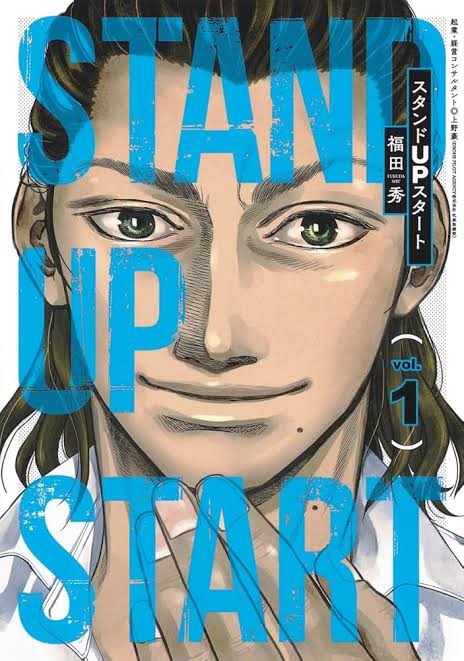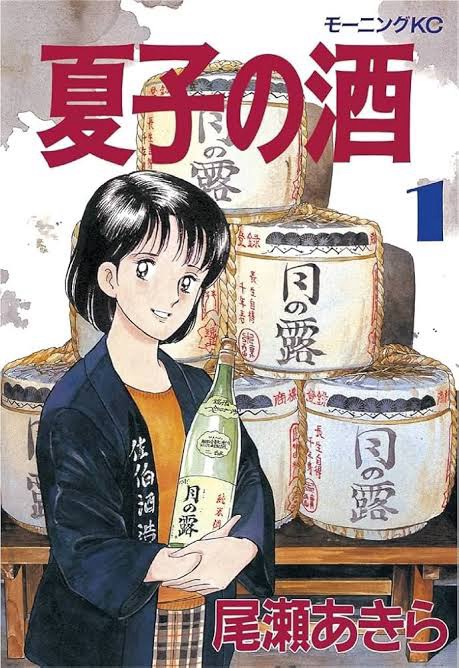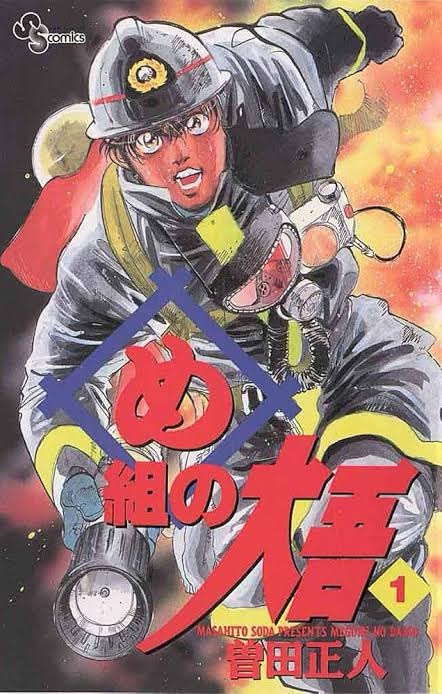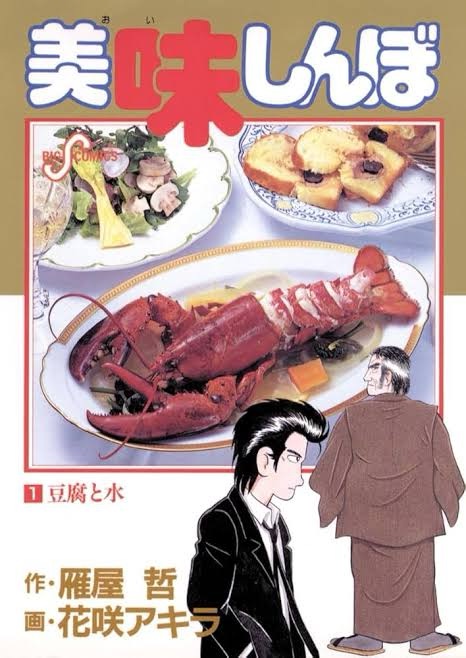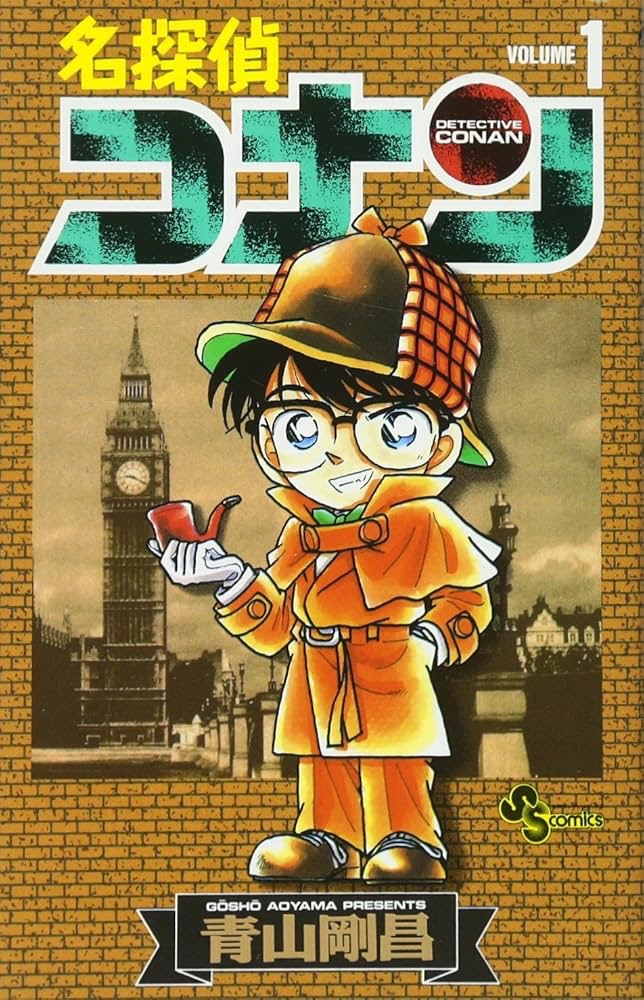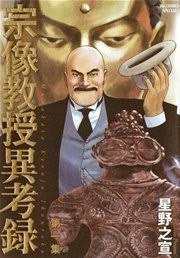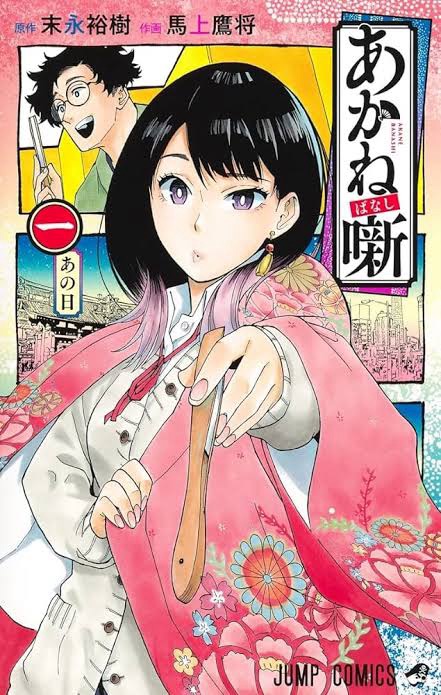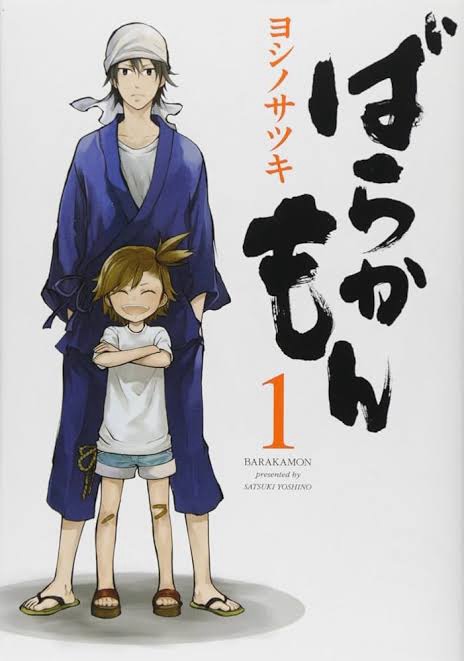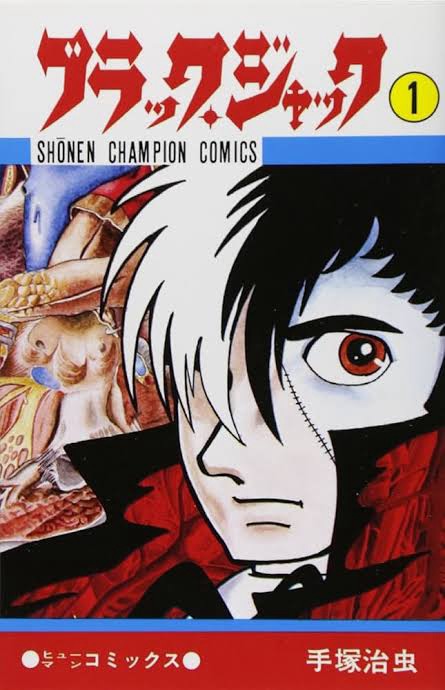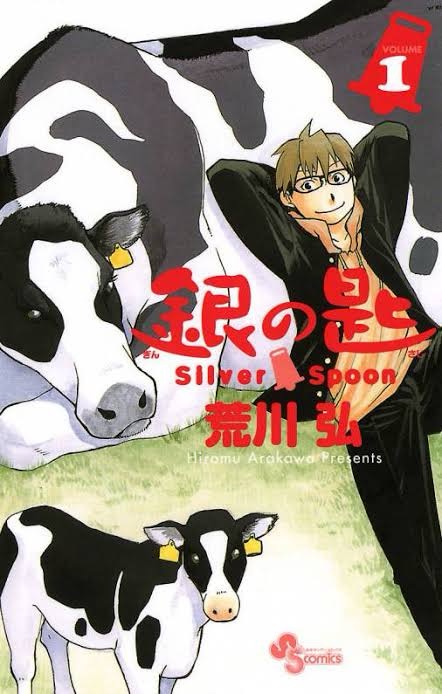挑戦と起業の重要性を漫画から学ぶ
『スタンドアップスタート』(原作:福田秀)は、挑戦と起業の精神をテーマにしたビジネス漫画です。この作品は、読者に勇気とビジネスに対する新しい視点を提供し、教育的な要素を豊富に含んでいます。今回はこの作品を通じて、起業精神や挑戦する心の重要性を学ぶ方法についてご紹介します。
『スタンドアップスタート』とは?
主人公・三星大陽(みほし たいよう)は、人々に起業という形で「再スタート」を促す投資家です。彼は、人の可能性を見抜き、社会から見放された人々でも挑戦できる場を作り出すストーリーテラー。個性豊かなキャラクターたちが、それぞれの夢や課題を抱えながら成功を目指していく様子が描かれています。
この作品が教育に役立つ理由
1. 起業の実践的な知識を学べる
『スタンドアップスタート』では、資金調達や事業計画、投資家との交渉術といったビジネスの基礎が描かれています。読者は物語を通して、実践的な起業ノウハウを学ぶことができます。
例:事業計画書の重要性を説いたシーンでは、具体的なアイデアをどのように形にするかが詳細に説明されています。
2. 失敗を恐れない精神を養う
三星は「失敗しても再スタートを切る勇気が大切だ」というメッセージを繰り返し伝えています。これは読者に、自分の可能性を信じて挑戦する心を教えてくれます。教育現場でも、失敗を恐れず試行錯誤することの重要性を伝える材料になるでしょう。
3. 多様なキャラクターが自己実現のヒントを提供
物語の中で登場するキャラクターたちは、それぞれ異なる背景やスキルを持っています。例えば、職を失った中年男性や若手エンジニアが、自分の強みを活かして新しい道を切り開く様子は、多様性を重視する現代教育にも役立ちます。
注目シーンと学び
• 三星がホームレスに声をかけ、起業のきっかけを作るシーン
社会から外れた立場の人でも、才能や経験を活かして成功できる可能性があることを強調しています。
• 資金調達の交渉場面
ビジネスの実践的な交渉術を、ドラマチックに学ぶことができます。相手のニーズを理解し、説得力のある提案をするスキルが具体的に描かれています。
• 失敗から再スタートを切るエピソード
挫折を乗り越えるための心構えや戦略を、感動的に教えてくれるシーンが随所にあります。
教育的なポイント
• ビジネスと自己表現の融合
自分の強みや情熱を活かして、新しい道を切り開く大切さを学べる。
• リーダーシップとコミュニケーションスキル
他者の信頼を得るためのリーダーシップや、円滑なコミュニケーションの重要性が強調されています。
• キャリア教育に最適
学生や若い世代が、働くことや起業について考えるきっかけになる作品です。
まとめ
『スタンドアップスタート』は、挑戦と自己実現をテーマにした教育的価値の高い作品です。失敗を恐れず、再スタートを切る勇気を持つ大切さや、ビジネスの実践的な知識を楽しく学ぶことができます。この漫画を通して、読者は「挑戦する心」と「自分を信じる力」を育むことができるでしょう。
ぜひこの作品を手に取って、新たな一歩を踏み出すインスピレーションを得てください!