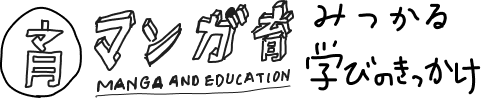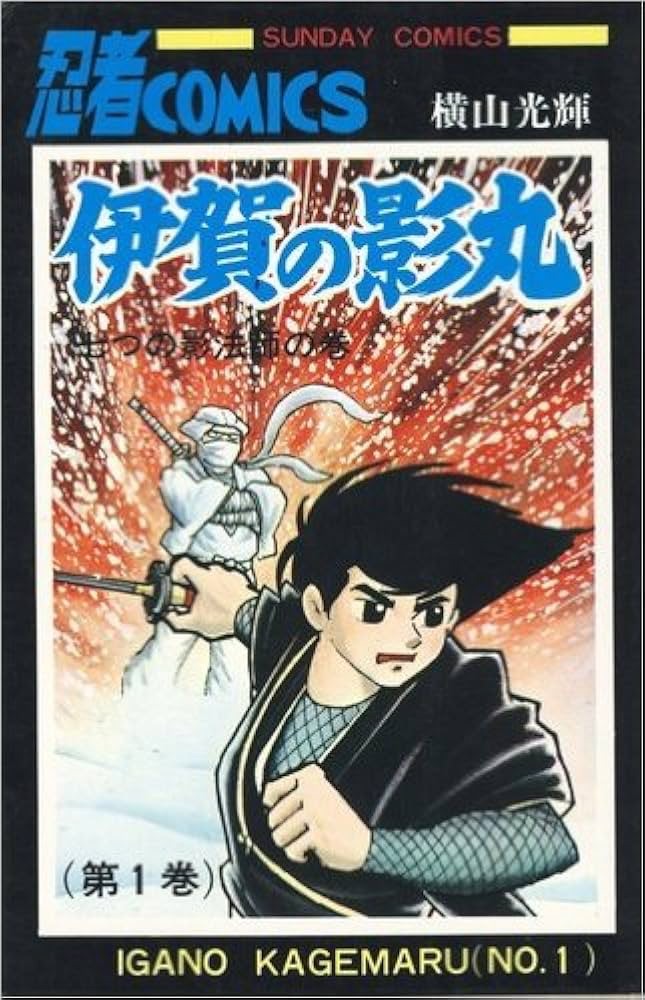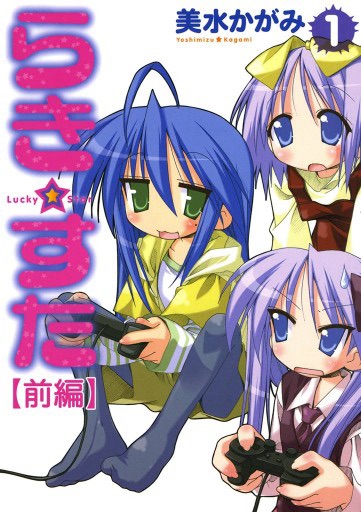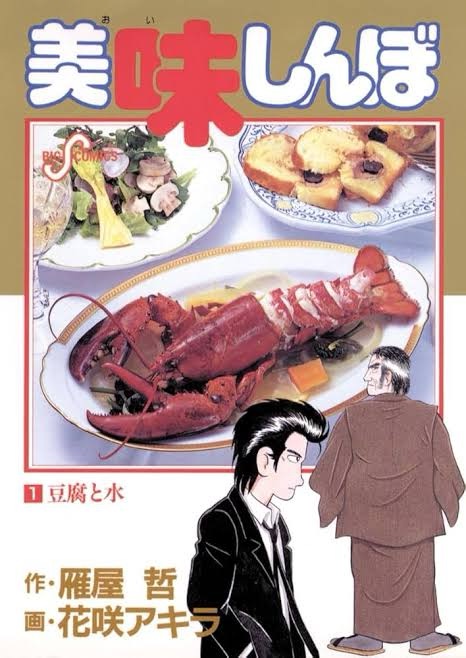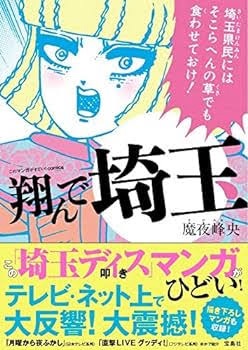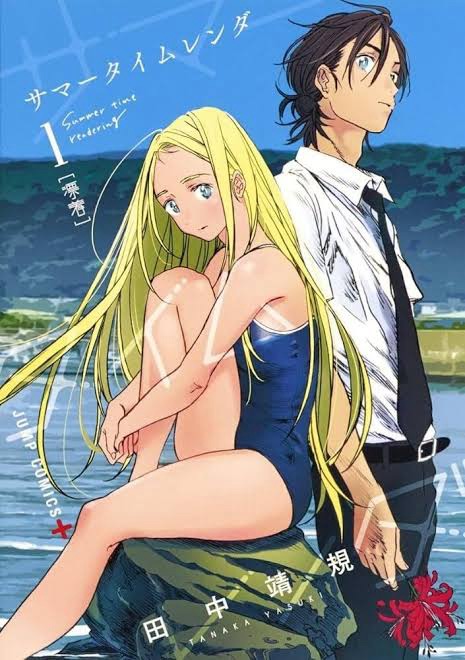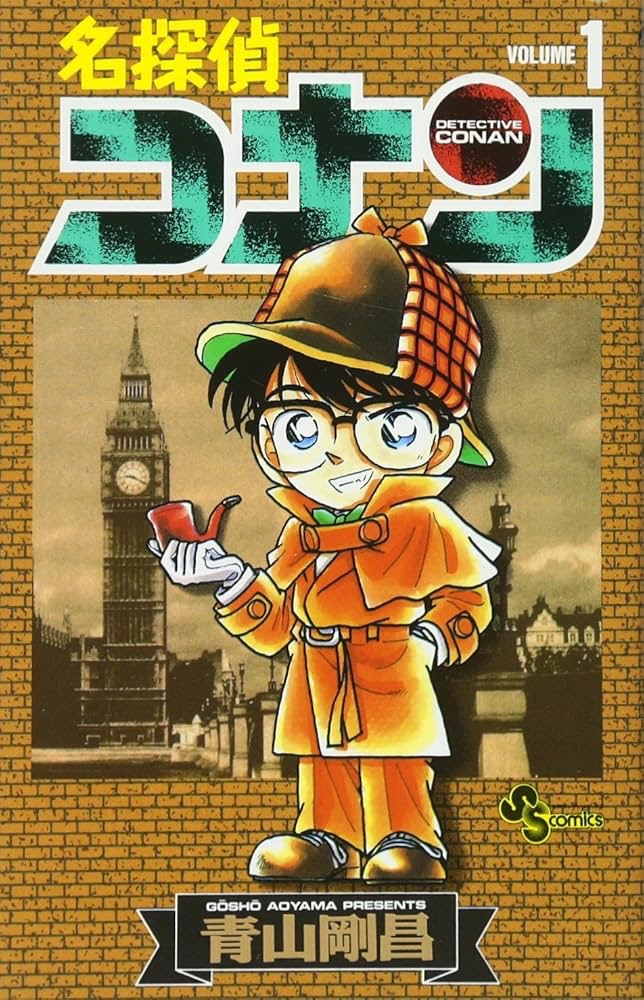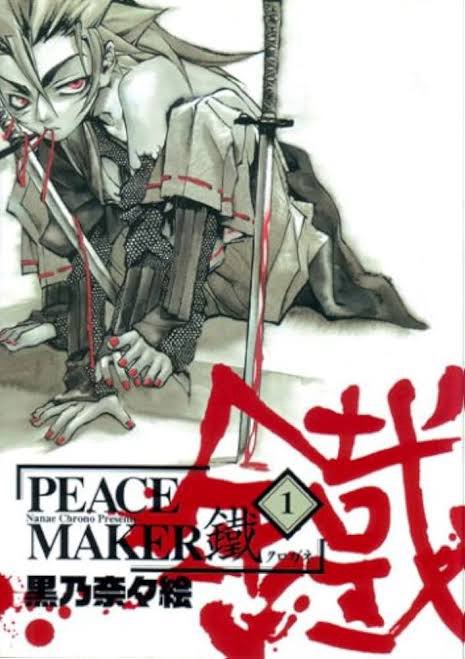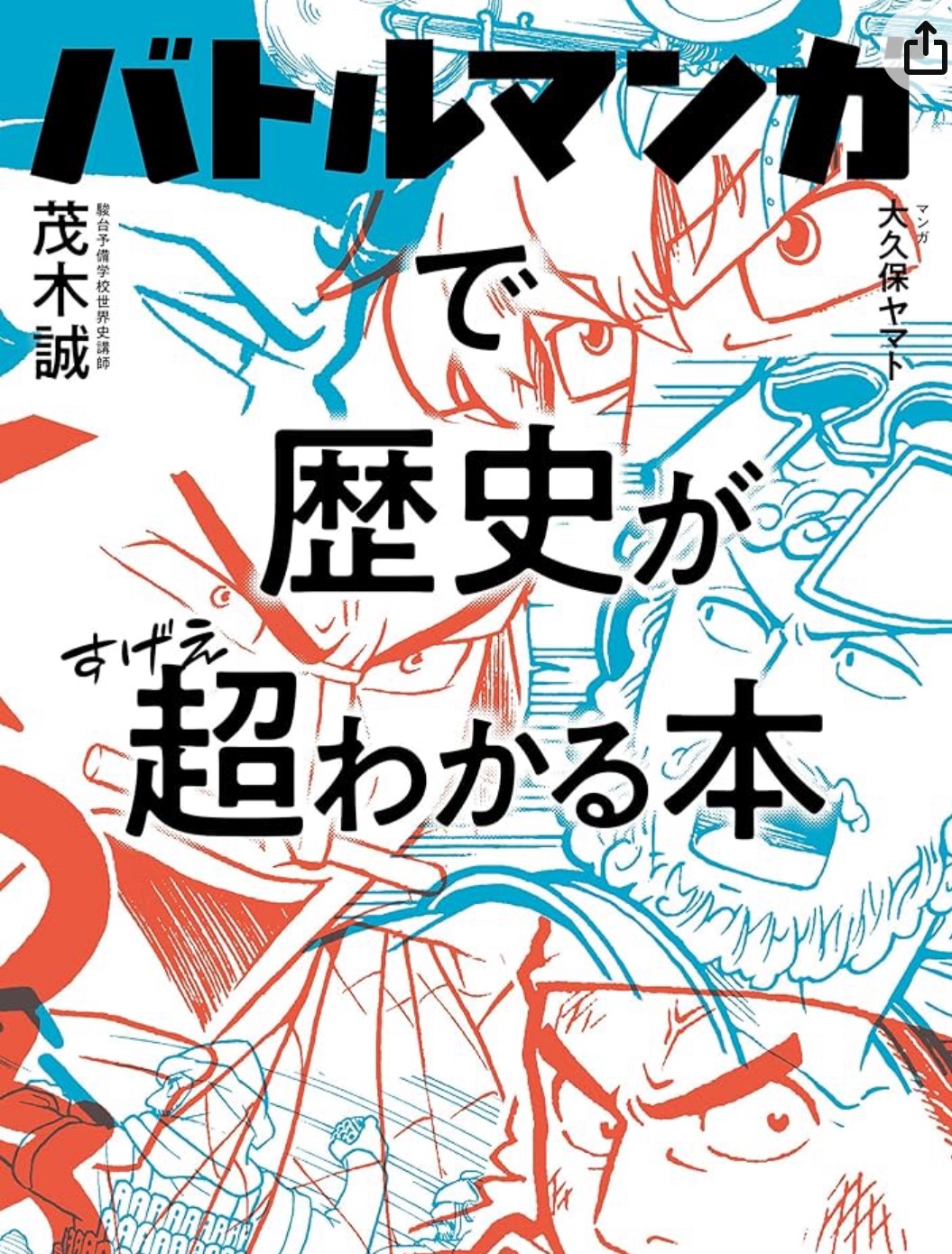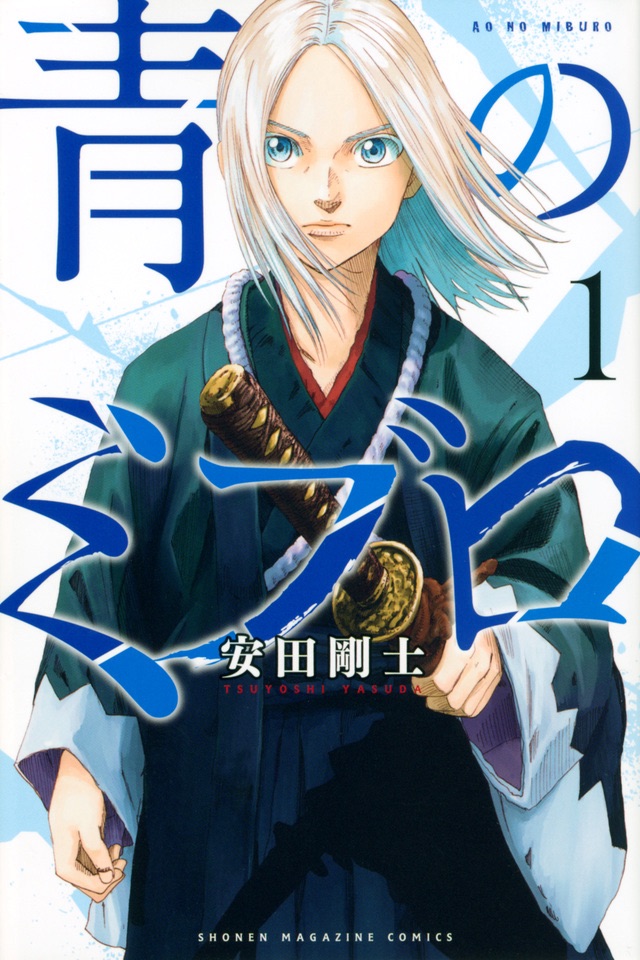青森県は、豊かな自然と独自の文化が息づく地域です。そんな青森県を舞台にした漫画『ふらいんぐうぃっち』は、魔女の少女が青森で過ごす日常を描きながら、地域の魅力を伝えています。この作品を通じて、青森県の自然や文化、人々の温かさを学んでみましょう。
漫画『ふらいんぐうぃっち』が青森県の教育に役立つ理由
1.青森県の自然や風景が美しく描かれている
作品内では、青森県の四季折々の風景や自然が丁寧に描写されています。特に、田園風景や山々、海など、青森の豊かな自然環境がリアルに再現されており、読者は青森の美しさを視覚的に楽しむことができます。
2.地域の文化や風習に触れることができる
作中には、青森県の伝統的な祭りや食文化、方言などが登場します。例えば、ねぶた祭りや郷土料理など、青森ならではの文化が物語の中で紹介されており、地域の風習や生活習慣を学ぶことができます。
3.人々の温かさやコミュニティの大切さを感じられる
主人公が青森で出会う人々との交流を通じて、地域社会の温かさや人と人とのつながりの大切さが描かれています。これにより、青森県の人々の人情やコミュニティの魅力を感じることができます。
印象的なシーンと学びのポイント
•青森の四季を感じるシーン
春の桜、夏の海、秋の紅葉、冬の雪景色など、青森の四季折々の風景が美しく描かれています。これらのシーンを通じて、青森の自然の豊かさや季節の移ろいを感じることができます。
•地域の祭りや行事に参加するシーン
主人公が地元の祭りや行事に参加する場面では、青森の伝統文化や地域の活気を感じることができます。これにより、地域の文化や風習への理解が深まります。
•地元の人々との交流シーン
主人公が地元の人々と交流し、助け合う場面では、青森の人々の温かさやコミュニティの強さを感じることができます。これにより、人と人とのつながりの大切さを学ぶことができます。
まとめ
『ふらいんぐうぃっち』は、青森県の自然や文化、人々の温かさを感じることができる作品です。魔女の日常を通じて描かれる青森の魅力は、読者に地域への興味や理解を深めさせてくれます。青森県の美しさや文化を学びたい方に、ぜひおすすめしたい作品です。