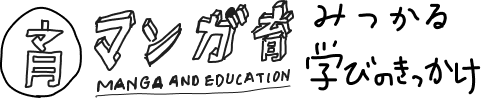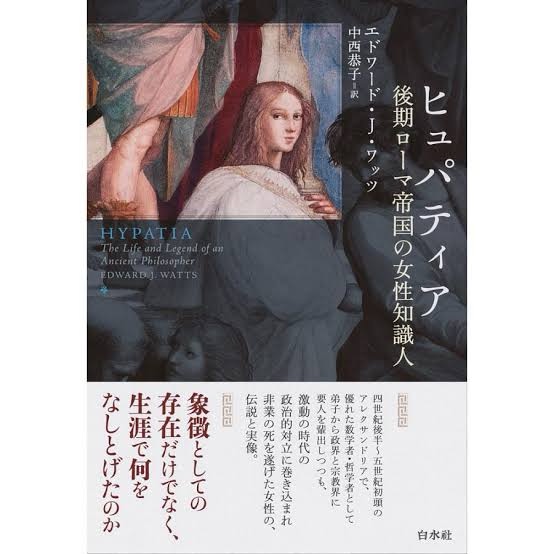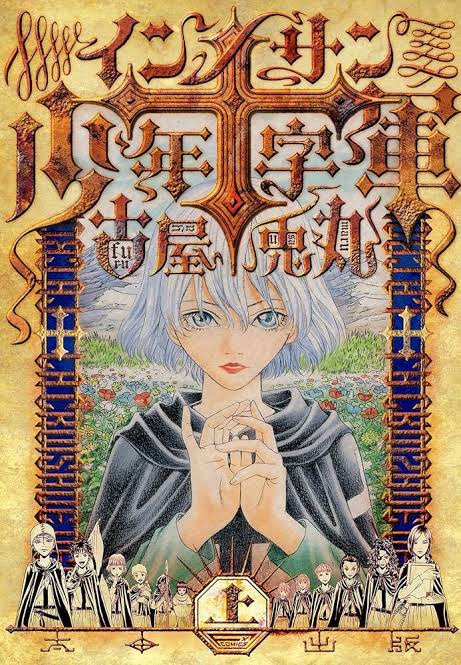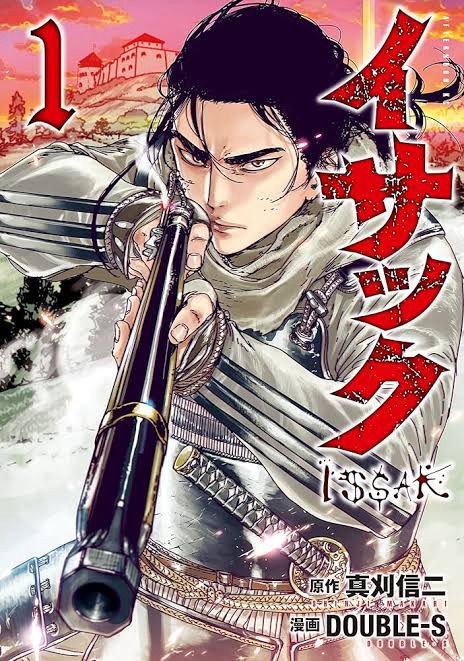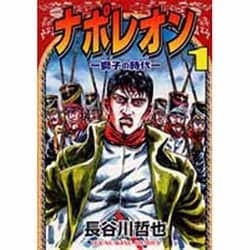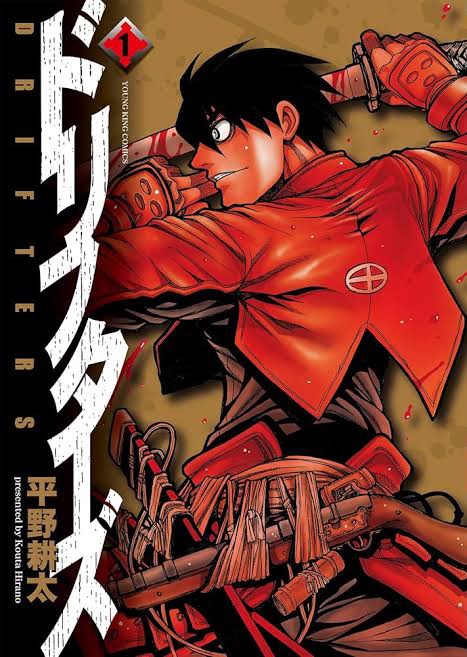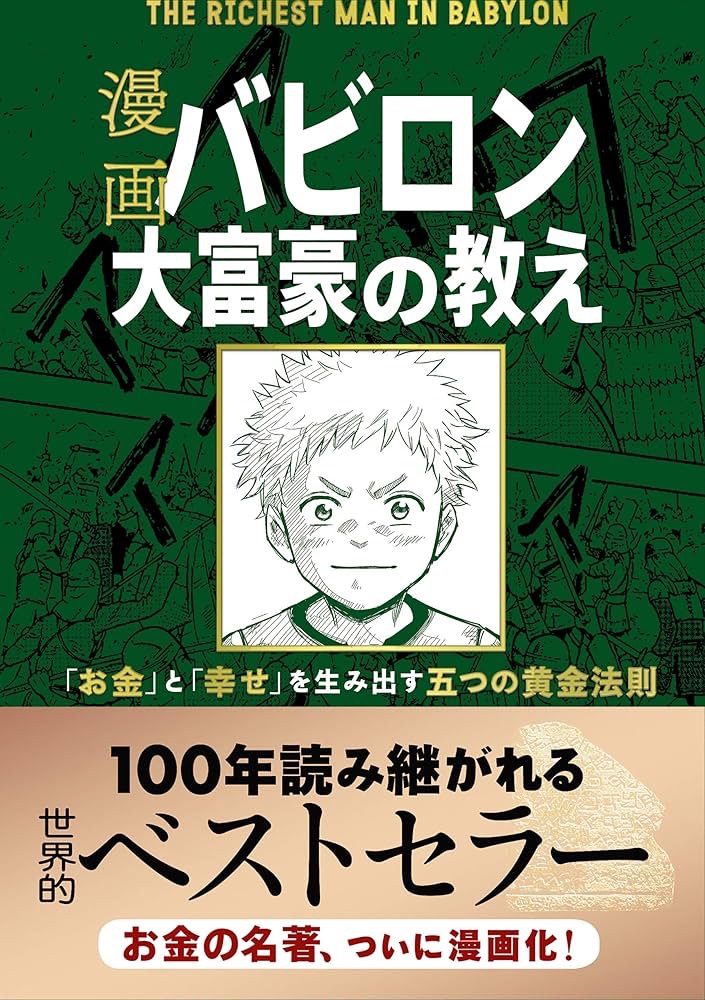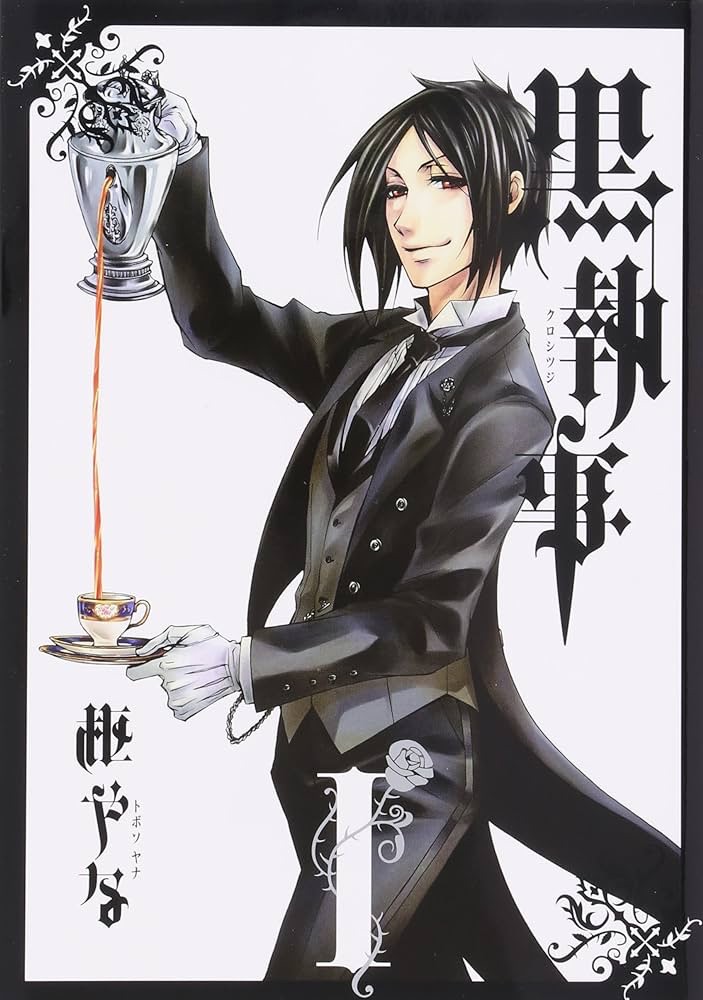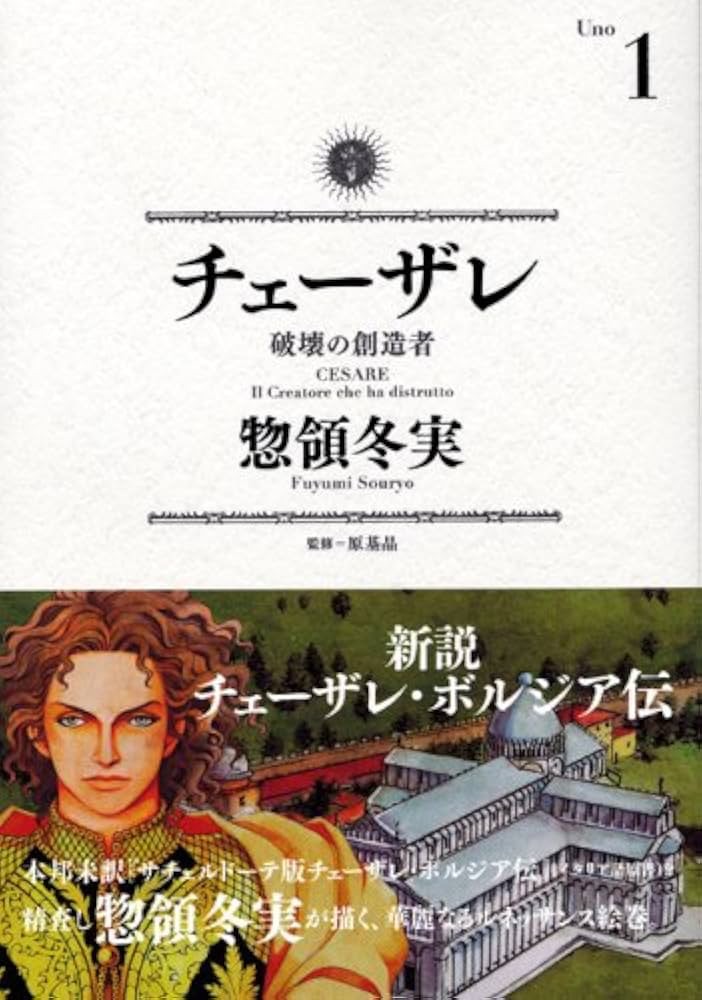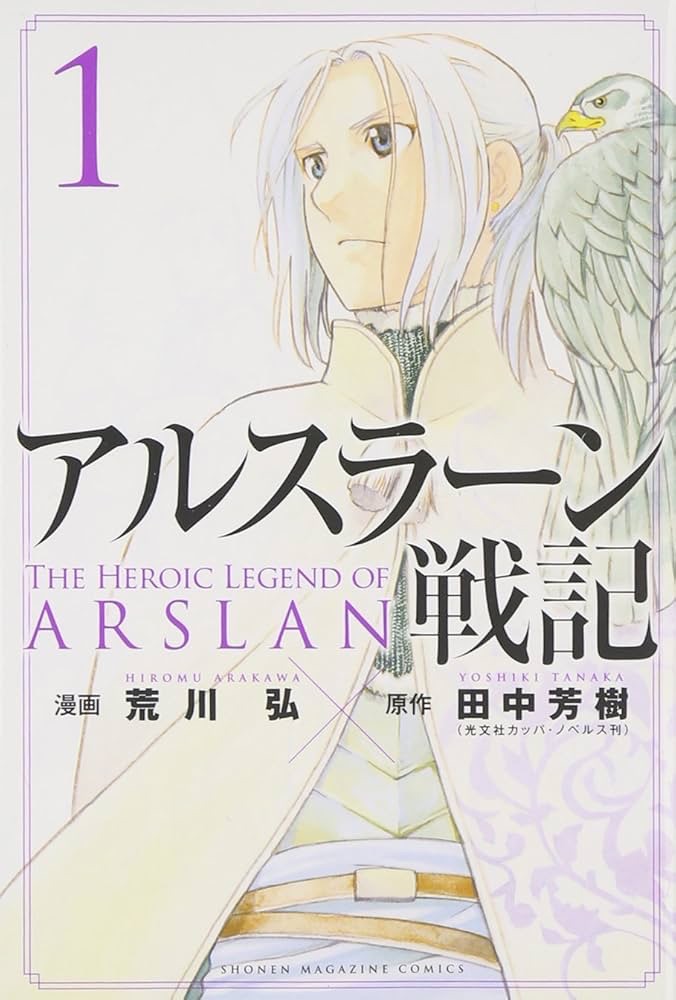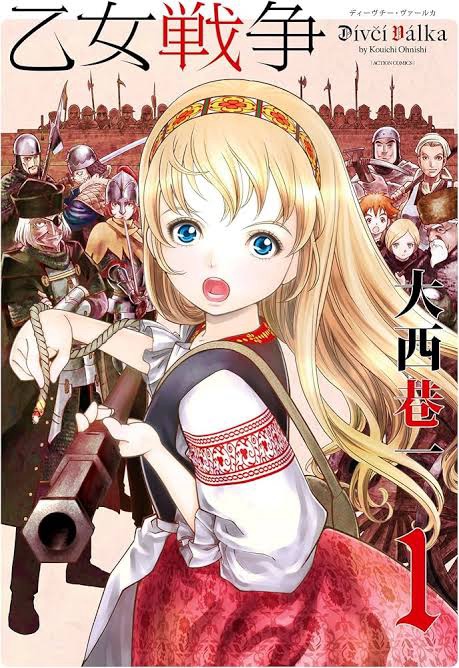古代アレキサンドリアの知の世界を描いた『ヒュパティア』は、歴史的事実に基づきながら、宗教と科学、知性と信仰の関係性について深い洞察を提供する教育的価値の高い作品です。
## 作品の概要
紀元後5世紀初頭のアレキサンドリアを舞台に、実在の女性哲学者ヒュパティアの生涯を描いた本作は、古代末期の地中海世界における学問と信仰の対立、そして知の探究の意味を問いかけます。
## 教育的価値
### 1. 古代アレキサンドリアの学術世界の再現
本作は以下の要素を緻密に描写しています:
– アレキサンドリア図書館の構造と運営
– 古代の数学・天文学研究の実態
– ネオプラトン主義哲学の教育
– 古代の教育システム
### 2. 多文化共生の歴史的モデル
作品は当時のアレキサンドリアの多様性を描きます:
– ギリシャ系住民とエジプト系住民の関係
– ユダヤ教徒、キリスト教徒、異教徒の共存
– 異なる哲学派の対話
– 東ローマ帝国の統治政策
### 3. 科学と信仰の関係性
本作は現代にも通じる重要なテーマを提示します:
– 合理的思考と宗教的信念の調和
– 学問の自由と社会的制約
– 知識の伝承と発展の意義
– 女性研究者の社会的位置づけ
## 教育現場での活用法
### 1. 歴史教育での活用
– 古代末期の地中海世界の理解
– アレキサンドリアの多文化社会の学習
– 古代の学問研究方法の把握
– 東ローマ帝国期の社会変動の理解
### 2. 科学史教育での活用
– 古代の数学・天文学の発展
– 科学的方法論の歴史
– 図書館の役割と知識の伝承
– 古代の教育システム
### 3. 哲学・倫理教育での活用
– 異なる信念との共存について
– 学問の自由と社会的責任
– 知識と権力の関係
– ジェンダーと学問の関係
## 現代への示唆
本作から学べる現代的な課題:
– 多文化共生社会の実現
– 学問の自由と社会的調和
– 女性の社会進出と教育機会
– 知の継承と発展の意義
## まとめ
『ヒュパティア』は、古代アレキサンドリアという特定の時代と場所を舞台としながら、現代にも通じる普遍的な問題を提起しています。学問と信仰、理性と感情、個人と社会の関係など、多層的なテーマを含む本作は、歴史教育にとどまらない幅広い教育的価値を持っています。