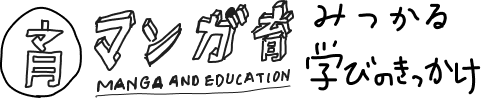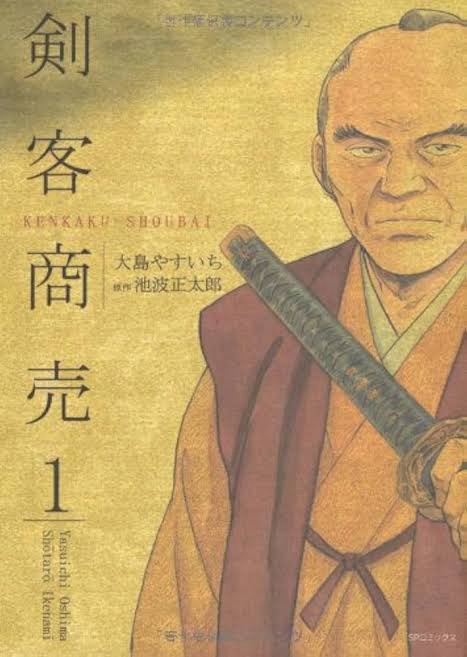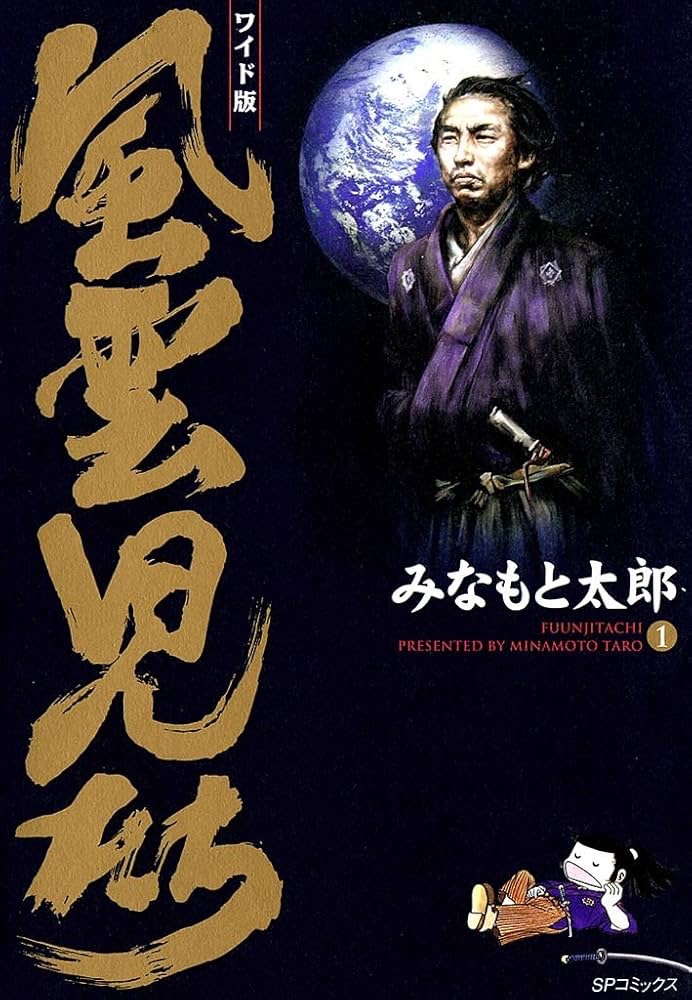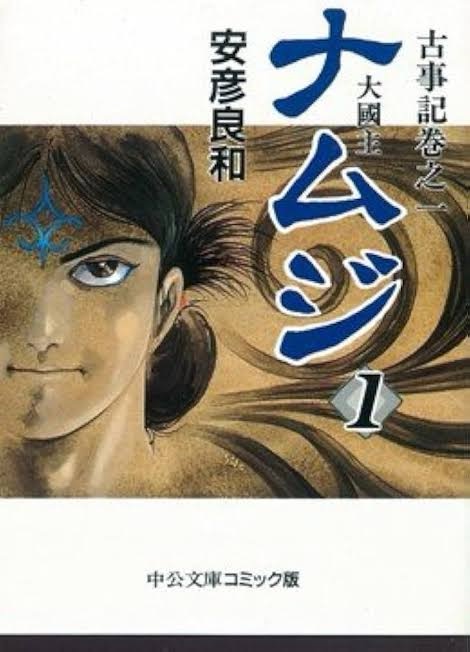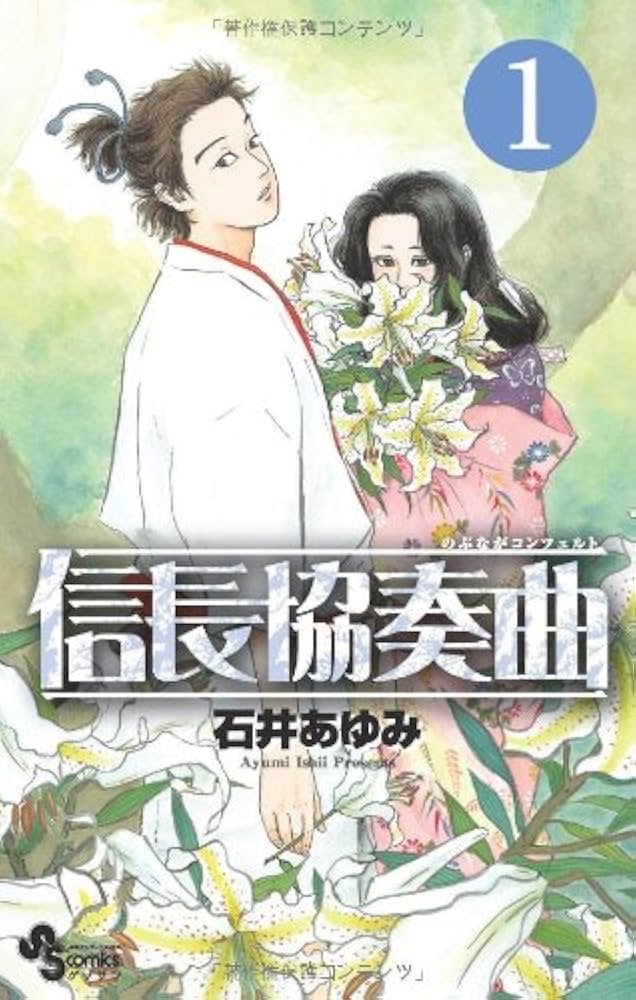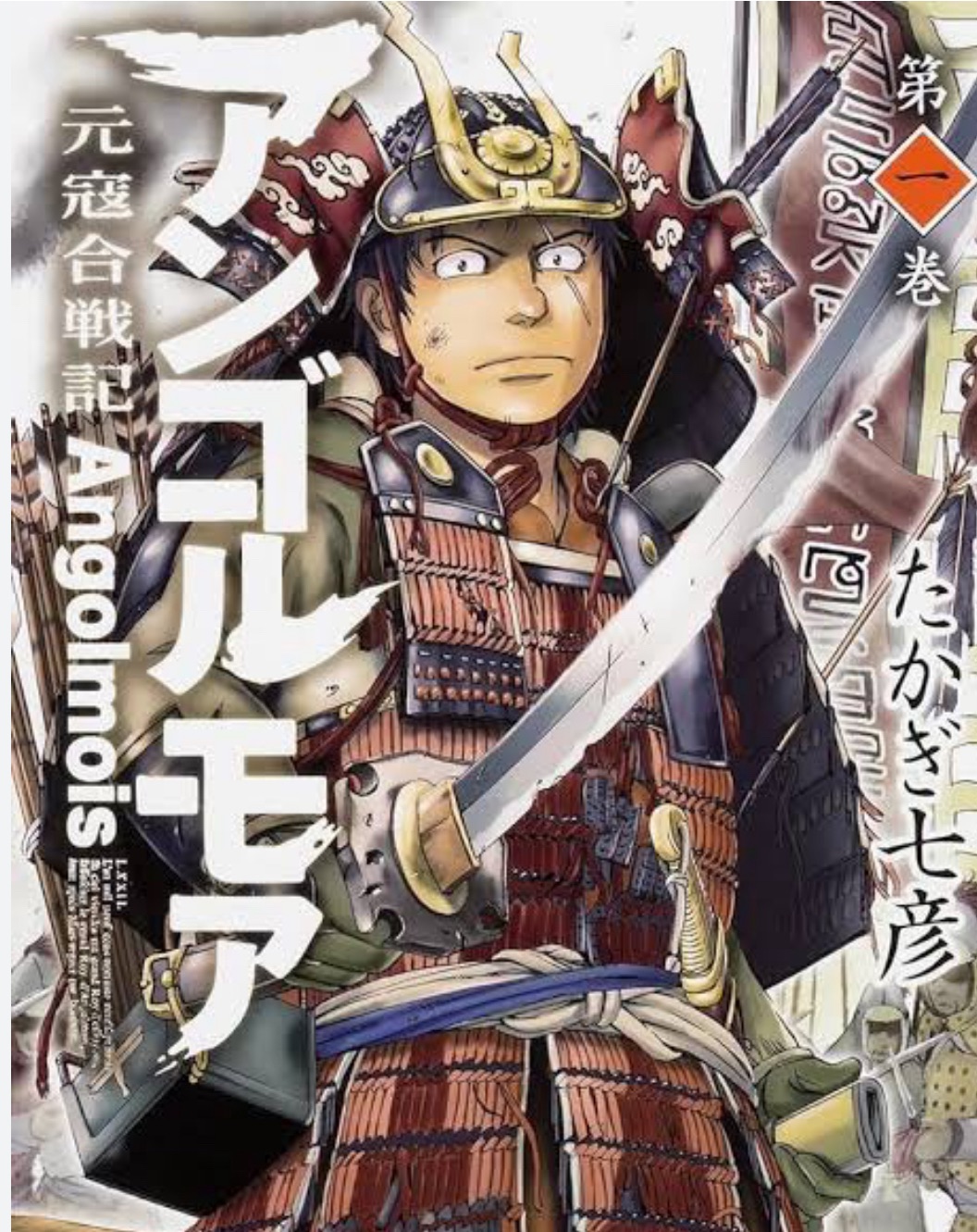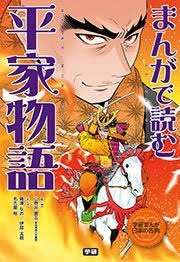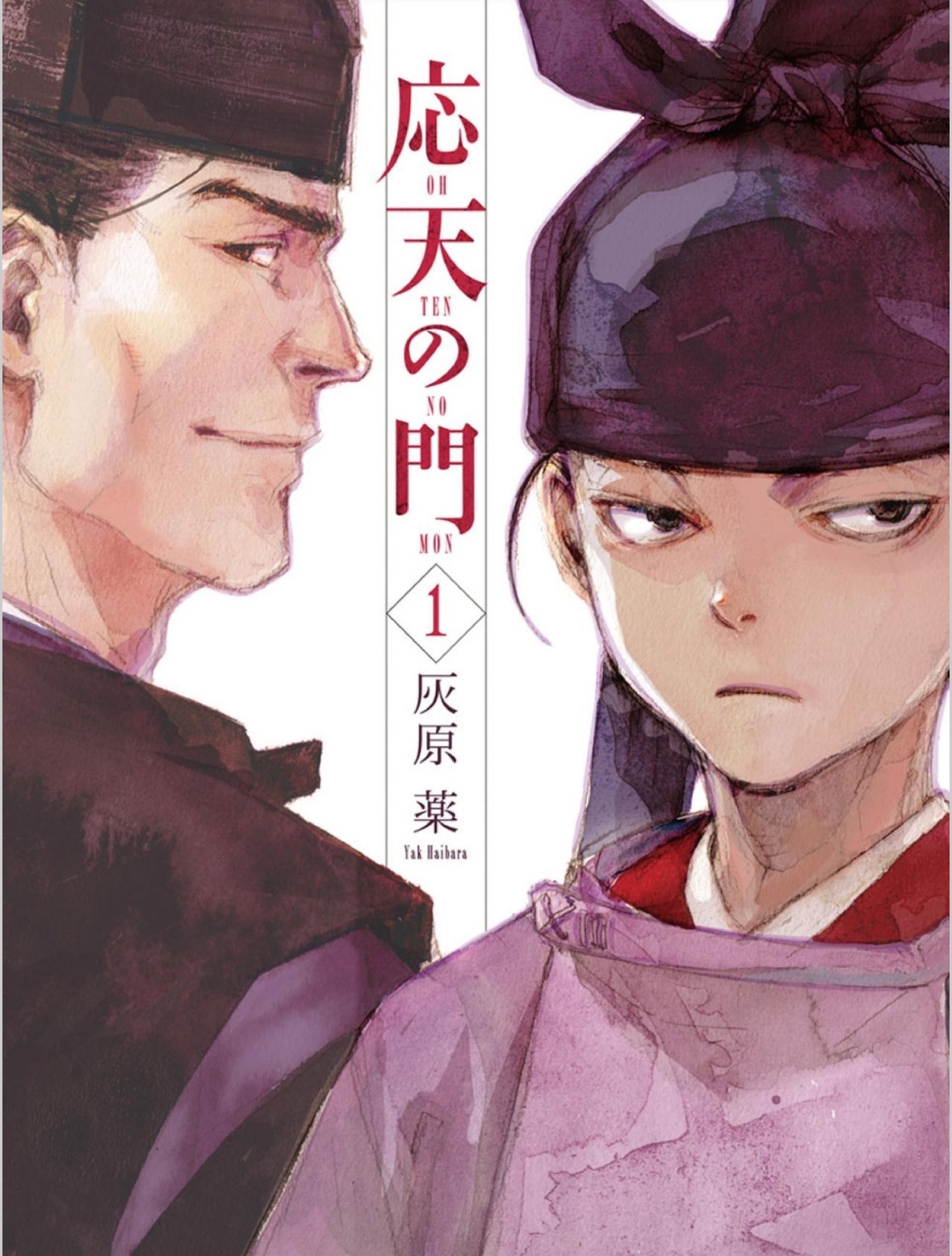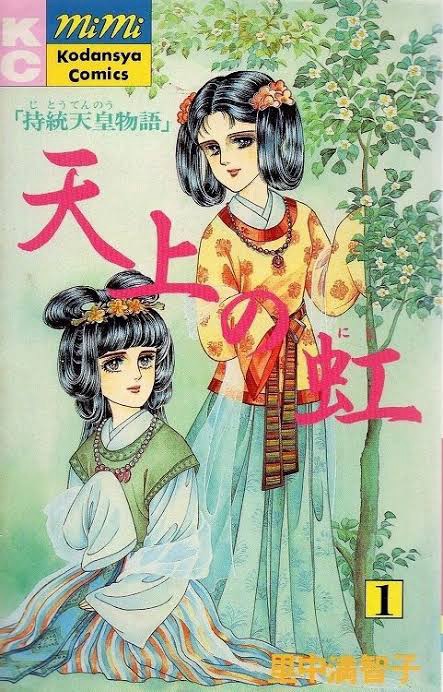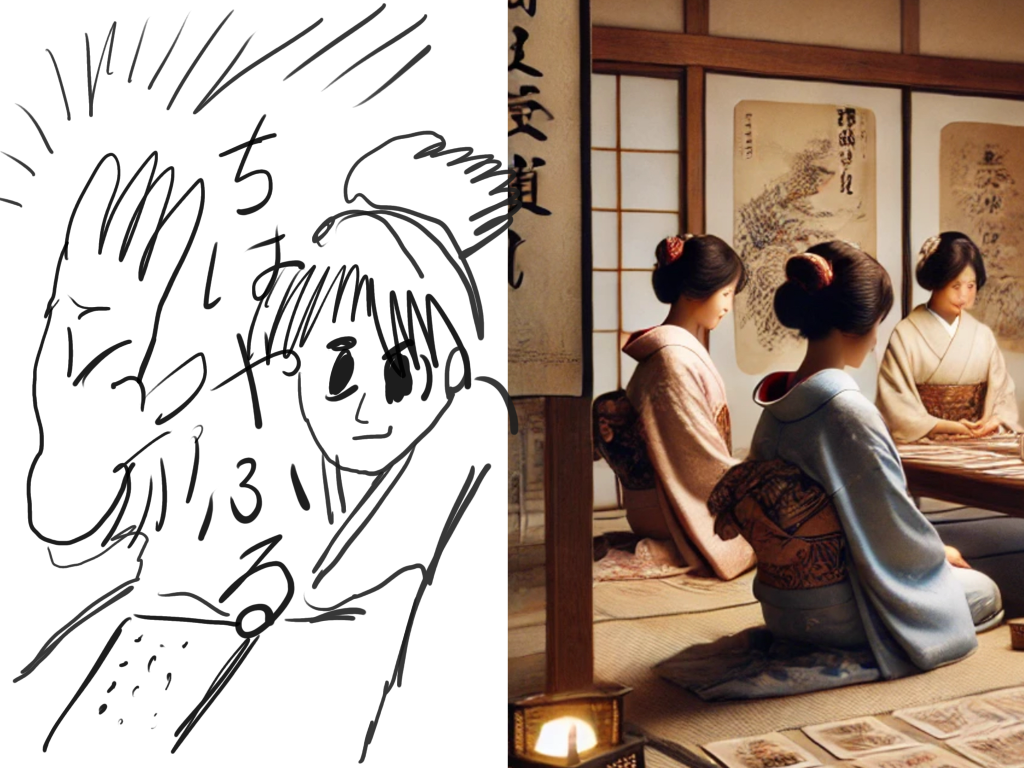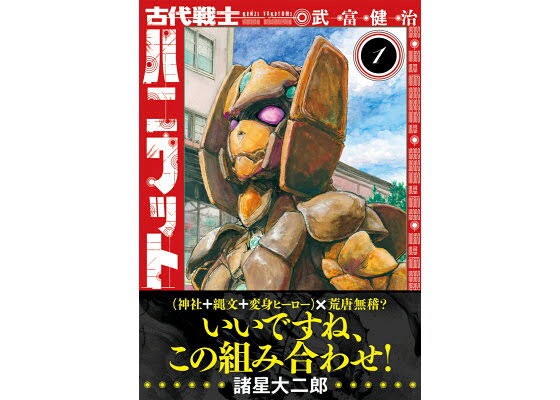『剣客商売』(原作:池波正太郎、漫画:大島やすいち)は、18世紀の日本、特に江戸時代中期の武士や剣客たちの日常を描いた人気シリーズです。江戸時代の平和な時代における武士たちの生き様を通して、当時の社会や文化を深く知ることができる作品です。剣豪の秋山小兵衛とその息子・大治郎が主人公で、武士としての誇りを持ちながらも、現実的な生活と人間関係に苦闘する姿が描かれています。
1. 江戸時代中期の武士社会
18世紀の江戸時代は、戦国時代のような戦乱が収まり、武士たちは戦場での活躍の機会が減少し、主に行政や警備の仕事に従事するようになりました。『剣客商売』では、戦うことが主な役割であった武士たちが、平和な時代にどのようにして新しい役割を見出しながら生活していたかが描かれています。秋山親子は剣客として生活しながら、時に事件に巻き込まれたり、人間関係の中で葛藤したりします。この作品を通じて、当時の武士社会の現実と理想とのギャップが見えてきます。
2. 武士道と生活のリアリティ
『剣客商売』では、剣の道を追求する武士たちの姿が描かれる一方で、彼らが直面する日常生活の現実も細かく描写されています。特に、家計を支えながら剣の道を守るための苦労や、平和な時代における武士道の在り方に対する疑問などがテーマとなっています。秋山小兵衛のように、剣術を極めながらも柔軟に生きる武士の姿は、18世紀の江戸時代に生きた武士たちがどのようにして武士道を守りつつも現実に適応していったかを考えさせられます。
3. 江戸時代の町人と武士の関係
18世紀の江戸では、武士だけでなく、町人階級も重要な役割を果たしていました。『剣客商売』では、武士と町人が共存する社会の中で、互いに協力しながら生活していく様子が描かれています。町人文化の発展も描かれ、武士が町人と関わることでどのように影響を受け、また与えたのかを知ることができます。18世紀は、武士だけでなく、商業や文化が繁栄した時代でもあり、この作品はその両面をうまく取り入れています。
4. 剣術の美学と実戦
『剣客商売』のもう一つの重要な要素は、剣術の描写です。18世紀の武士たちは、実戦での戦闘の機会が減ったとはいえ、剣術の修練を続け、名誉を守るために日々稽古に励みました。秋山小兵衛や息子の大治郎が剣術を通じて様々な人々と出会い、時には対決する姿が描かれ、剣術が単なる武力ではなく、精神性や美学を伴ったものであったことが伝わってきます。
注目シーン: 親子の絆と剣術の伝承
『剣客商売』の中でも特に注目すべきシーンは、秋山親子の絆です。父である小兵衛が、息子の大治郎に剣術の技術や生き方を教え、親子の絆を深めていく様子は、この作品の中心的なテーマの一つです。剣術だけでなく、武士としての誇りや価値観がどのように次世代へと受け継がれていくのかが描かれています。
18世紀の日本から学ぶ教訓
『剣客商売』を通じて学べるのは、平和な時代における武士の役割や、武士道の精神の変容です。戦乱の時代が終わり、武士たちは戦場から日常生活へとその活動の場を移しましたが、それでも誇りを持って生きるためにどのような選択をしていたのかが描かれています。この作品を通じて、18世紀の武士たちの葛藤と、その中で守り続けた価値観について理解を深めることができるでしょう。
まとめ
**『剣客商売』**は、18世紀の江戸時代中期を舞台に、剣豪・秋山親子を中心に武士の生活や社会を描いた歴史漫画です。平和な時代における武士の苦悩や、人間関係、剣術の美学が巧みに描かれており、当時の日本の社会を学ぶ上で非常に興味深い作品です。江戸時代の武士道や町人文化に興味がある方にとって、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。